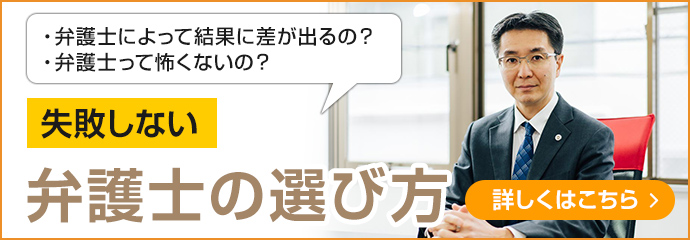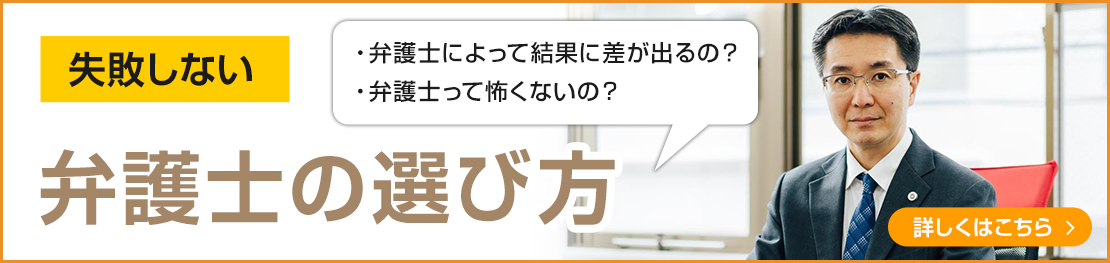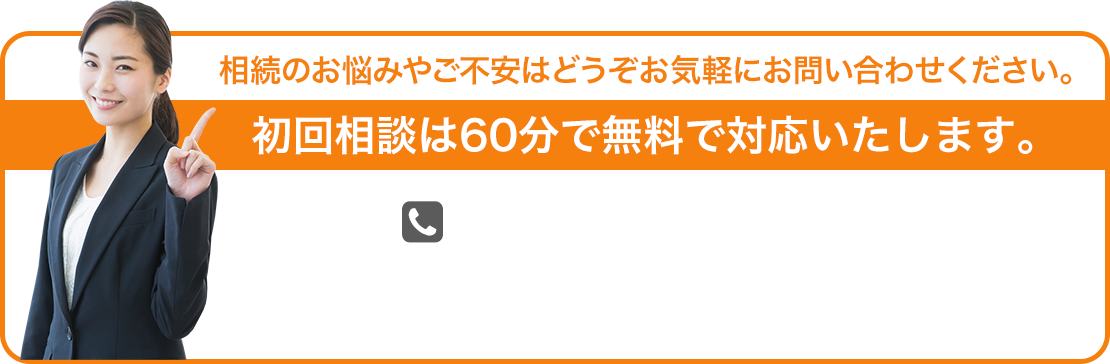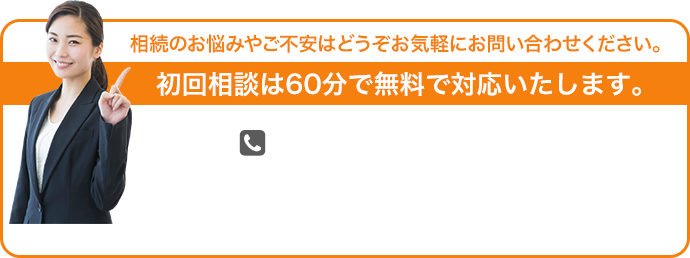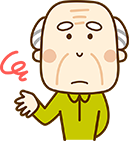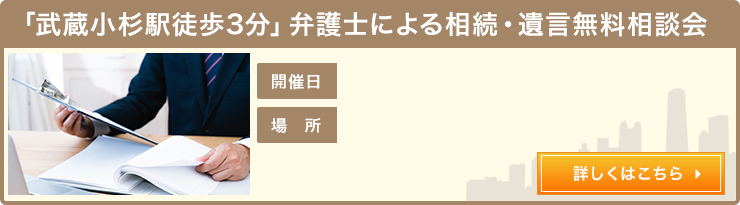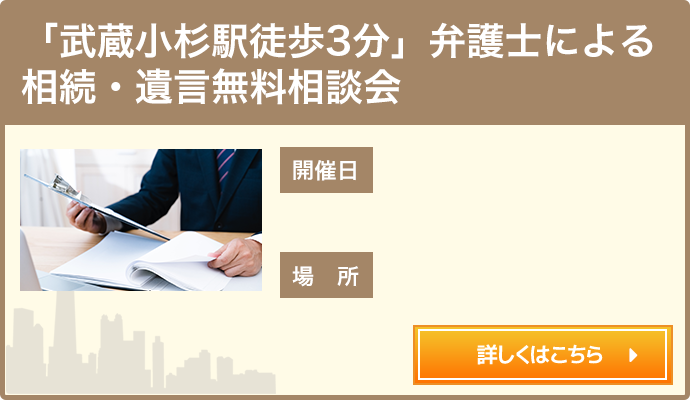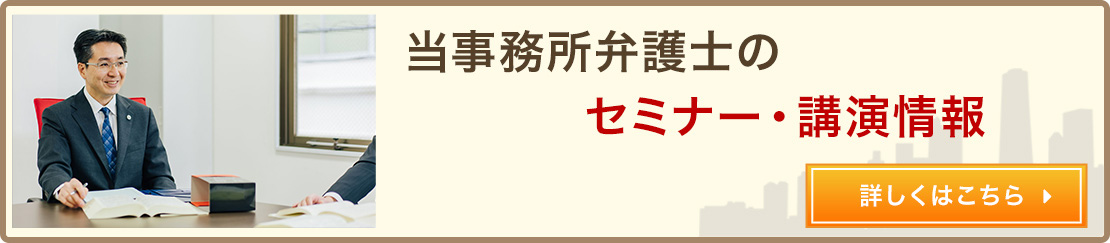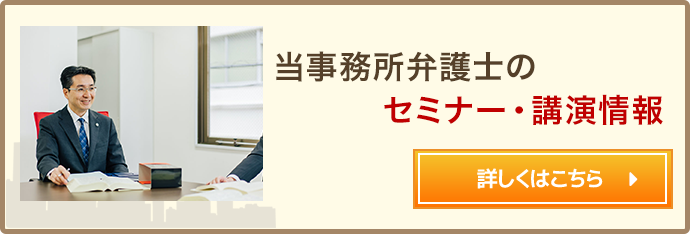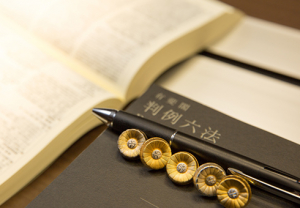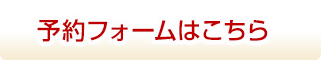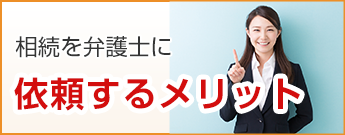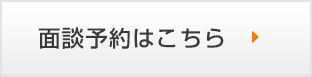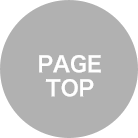不動産相続の注意点と流れについて弁護士が解説
- 2025.12.24
相続の中でも特にトラブルになりやすいのが不動産相続です。不動産は現金のように分けることが難しく、評価の仕方や管理方法について相続人間で意見が分かれることが多いためです。
この記事では、不動産相続でよくあるトラブルや、不動産の種類ごとの注意点、相続手続きの流れ、トラブルを未然に防ぐ方法、そして弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
不動産相続でよくあるトラブルとは
不動産相続では、以下のようなトラブルが頻発します。
相続人間での分割方法を巡る対立
不動産の評価額についての意見の相違
誰が不動産を取得し、他の相続人にどのように代償金を支払うかの問題
共有状態が長引くことでの管理・売却の困難
生前の親族による不公平な贈与の有無に関する争い
不動産の相続において、いくつかのモデルケースをお示しします。
事例①
父親が亡くなり、母親と3人の子どもが相続人となったケース。長男は実家で両親と同居しており、家を取得したいと主張。しかし、他の兄弟は「不公平だ」と反発。代償金の額で対立し、家庭裁判所の調停にまで発展しました。結果として調停での解決となったものの、兄弟間の関係は大きく損なわれました。
事例②
父親が亡くなったが遺言書が見つからず、家族が遺産分割協議を開始。財産関係について生前家族は関与してこなかったため、調査を行ったところ、別荘や貸地などの不動産が複数判明しました。中には空き地や、遠方で管理の行き届いていない不動産もありました。そこで、税理士・司法書士と連携して評価額や登記を整理し、相続人の誰も取得を希望しない不動産については処分した上、長男が実家を取得し、他の相続人に代償金を支払う形で合意が成立しました。
事例③
資産家の父親は、二世帯住宅で長男家族と同居していましたが、他の相続人との間で揉めないように、公正証書遺言を作成していました。遺言では長男とその家族に自宅を相続させる代わりに、生命保険で他の子ども達に補償する仕組みにしていたため、父さんが亡くなった際、トラブルは発生せずスムーズに相続が進みました。
不動産の種類別の注意点
不動産といっても、その種類によって相続時の注意点が異なります。
自宅(居住用不動産) ~事例①、事例③のケース~
相続人の一部が居住している場合、明け渡しや住居費用の負担が問題になります。事例①のケースでは、長男が相続財産である自宅に居住し続けることになりましたが、近年の不動産価格の高騰を受けて、代償金の算定価格も上昇する傾向があります。今回のケースのように不動産の売却を避けたい場合、現実的に金額を用意できるかは問題になります。また、相続税について小規模宅地等の特例による相続税評価の軽減が適用されるか否かの確認も必要です。
賃貸用不動産事例 ~事例②のケース~
賃貸契約が継続している場合、賃料収入の扱いや管理責任の所在が重要になります。借地権・借家権の存在も紛争が複雑となる要因です。また、収益物件の評価や相続税の計算、管理体制の継承も論点になります。
空き地・空き家 ~事例②のケース~
売却予定がある場合でも、売却までの間の管理や税負担についての話し合いが必要です。放置すると固定資産税や草木の管理などで周辺住民とのトラブルになる可能性もあります。
共有名義の不動産
相続時のトラブルに限らないところですが、不動産を共有名義としてしまうと、売却や修繕の決定に全員の同意が必要になるなど、運用上の制約が大きくなります。トラブル防止の観点からも、可能な限り共有状態を避けるべきです。
不動産相続の流れ
不動産を相続する場合、おおまかに次のような流れで進みます。
①相続人の確定
②遺言書の有無の確認(公正証書遺言、自筆証書遺言など)
③相続財産の調査(不動産の名義・評価額・ローンの有無など)
④遺産分割協議
⑤不動産の名義変更(相続登記)
⑥相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
不動産相続でトラブルを未然に防止する方法
・生前に遺言書を作成する(公正証書遺言が望ましい)
・家族信託の活用により、生前から不動産の管理や承継を明確にする
・不動産の評価や登記内容を事前に確認しておく
・相続人間で日頃からコミュニケーションを図っておく
また、生前贈与や不動産の売却を通じて、相続時の不動産の量や種類を調整しておくことも一つの方法です。特に賃貸物件などは、生前の売却や不動産を取得する会社を設立すること(=法人化)も検討する価値があります。
不動産相続を弁護士に依頼するメリット
不動産相続において弁護士が関与することで、以下のようなメリットがあります。
・相続人間の感情的対立を緩和し、中立的立場で円滑な協議を進める
・不動産の法的な評価や税務上の注意点を踏まえて適切な助言が可能
・遺言書作成や遺産分割協議書の作成など、将来的なトラブルを見据えた書面作成ができる
・訴訟や調停などの法的紛争にもスムーズに対応できる
特に相続人が多い場合や、不動産の価値が高い場合、また過去の親族関係に複雑な事情がある場合には、専門家のサポートが不可欠です。税理士・司法書士・不動産鑑定士との連携も弁護士を通じてスムーズに行えます。
不動産相続に関するお悩みは当事務所にご相談ください
不動産相続は、一歩間違えると家族関係の崩壊にもつながりかねないデリケートな問題です。当事務所では、相続案件を多数扱ってきた経験豊富な弁護士が在籍しており、お客様の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
生前の対策から相続発生後の手続き、協議、調停、訴訟まで幅広く対応可能です。また、初回相談では、不動産評価の方法や相続税の申告の可能性など、具体的なアドバイスも差し上げております。
不動産相続に関するお悩みは、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。

2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長