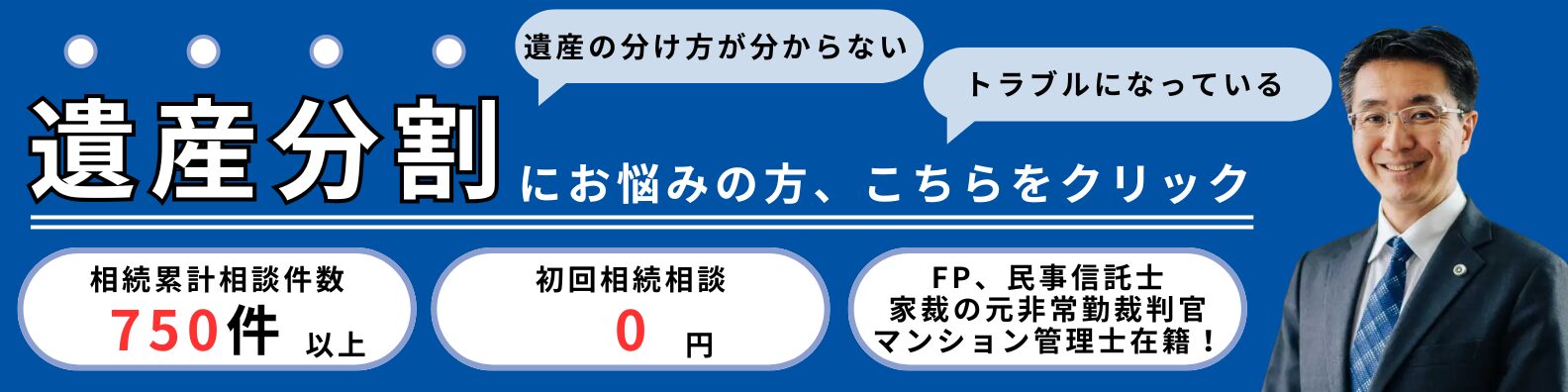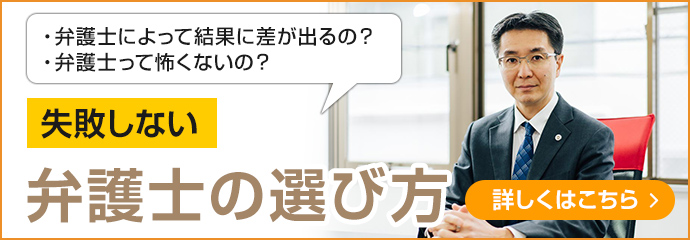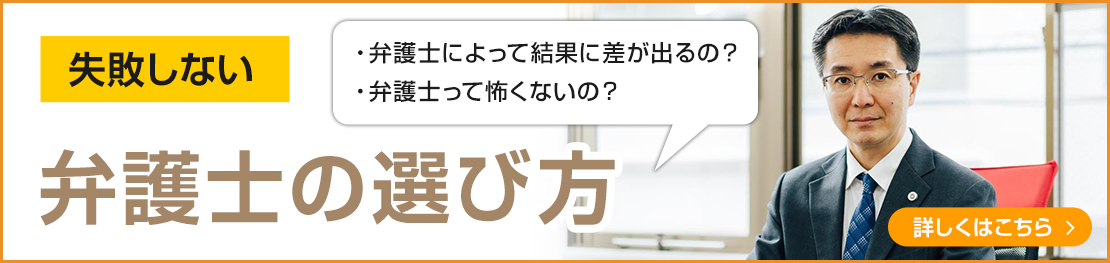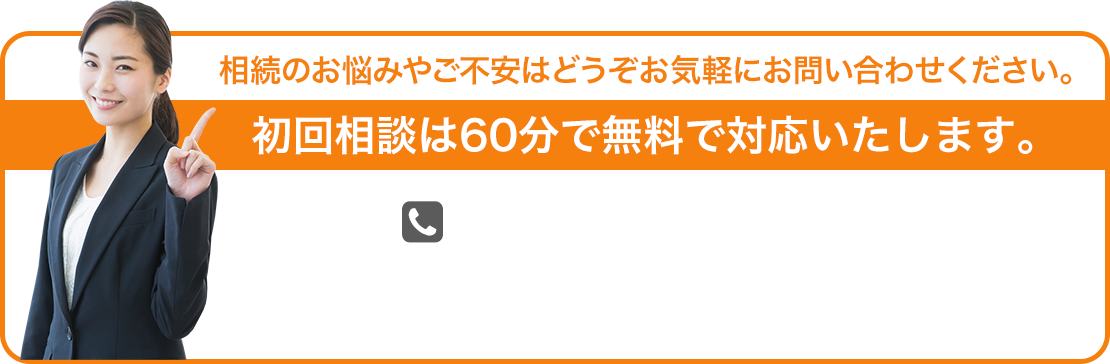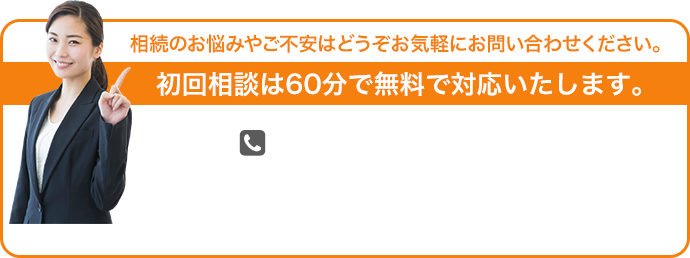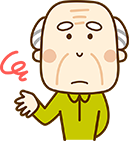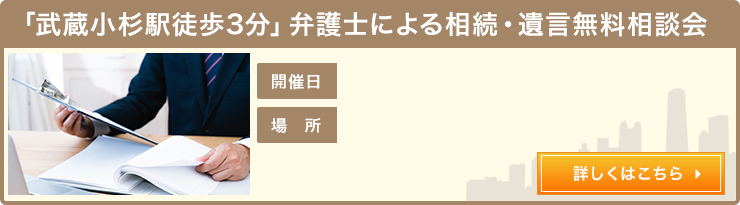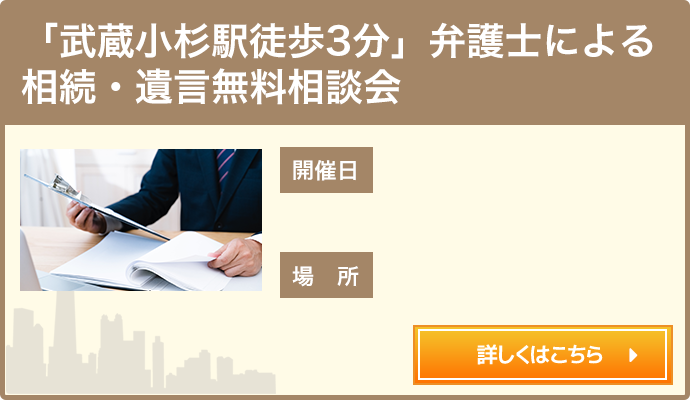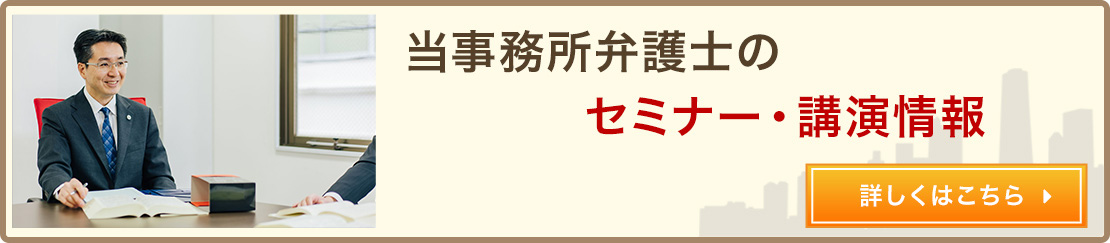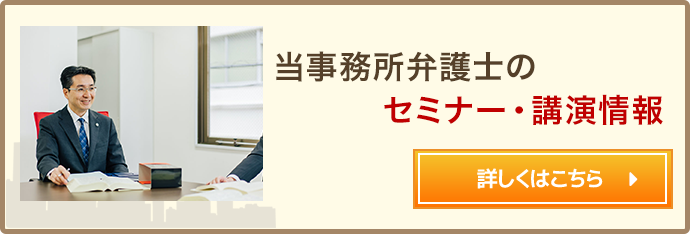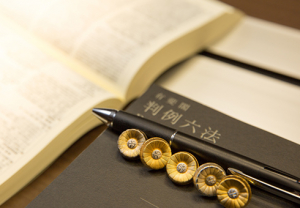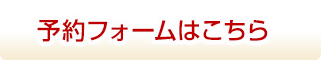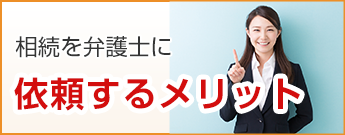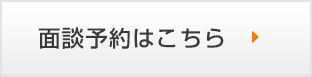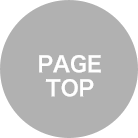遺産分割を自分で進める方法とそのリスクについて弁護士が解説
- 2025.12.16
相続が発生した際に、避けて通れないのが「遺産分割」です。
遺産分割をスムーズに進めることができれば、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。しかし、方法を誤ると、相続人間の対立が深刻化し、法的な問題へと発展するケースもあります。本コラムでは、遺産分割の基本的な流れや、自分で進める際の方法やそのリスク、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人の間で分ける手続きを指します。
被相続人が遺言を残さずに死亡し、かつ相続人が複数いる場合、相続財産は一旦、相続人全員の「遺産共有」の状態になります。この共有状態を解消し、各相続人の取り分を決定するのが遺産分割です。
遺産分割の方法は大きく分けて以下の3つで、基本的には、1→2→3の順番で進めていくことになります。
1協議分割:相続人全員で話し合い、合意の上で分割方法を決める。
2調停分割:協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停を行い、合意を目指す。
3審判分割:調停でも合意に至らない場合、裁判所が判断を下し、遺産分割を決定する。
遺産分割の方法と流れ
遺産分割は以下の流れで進められます。
-
1相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定します。
↓
2相続財産の調査:不動産、預貯金、株式などの財産、借金やその他負債を調査・確認します。
↓
3遺産分割協議の実施:相続人全員で話し合い、分割方法を決定します。
↓
4遺産分割協議書の作成:合意内容を文書化し、相続人全員が署名・押印します。その後の銀行手続や登記移転の手続を考えると実印での押印と印鑑証明書の添付が望ましい。
※当事者間で話ができない場合には、遺産分割調停を起こして、家庭裁判所において調停委員に間に入ってもらい話し合いによる解決を目指します(合意ができた場合、裁判所が調停調書を作成します)。
調停でも話し合いができない場合には、裁判所が審判を出してそれにしたがって遺産が分割されることになります。
↓
5財産の名義変更や手続き:銀行口座の名義変更、不動産登記の変更などを実施。各金融機関や法務局によって必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。
遺産分割は自分でできる?
遺産分割は、相続人同士で合意ができれば自分たちで進めることも可能です。
自分で進める場合のメリット
- 弁護士費用を節約できる
- 相続人同士で直接話し合うことで、スピーディーに解決できる可能性がある
- 相続人同士の関係が良好な場合、より円満な解決につながることがある
遺産分割を自分で行うリスクと注意点
遺産分割を自分で進める際には、以下のようなリスクが伴います。
-
相続人同士の対立
- 財産の分け方に不満が出ると、話し合いがまとまらなくなることがあります。特に、感情的な対立が生じると、第三者が入った場合には合理的な解決が可能な事案でも長期化・複雑化するリスクがあります。
-
相続人調査の不備
遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要ですが、相続人調査が不十分ですと、一部の相続人のみでの遺産分割協議となってしまい、その遺産分割協議書は無効となってしまいます。
法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等と、相続人の戸籍謄本を集める必要がありますが、この手続はかなり大変です。また、相続人の中に認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合、成年後見人等の選任が必要となる場合があります。
相続財産調査の不備
相続財産調査が不十分だと、一度合意した後にさらに相続財産について話し合いを行う必要が出てきてしまい、二度手間になります。また、財産だけではなく、借金についてもきちんと調査しておかないと、後から借金の方が多かったということにもなりかねません。一度、相続財産を取得した後には原則として相続放棄は出来ませんので、きちんと財産調査をする必要があります。
なお、相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続税や登記に関して問題が発生することがある
遺産分割協議をした後にも、本来しなければならなかった相続税の申告漏れや、不動産登記の不備(合意通りに登記が移転できない)などの問題が発生することがあります。特に、相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
遺産分割において、弁護士に依頼することで得られるメリットは多くあります。例えば、以下のようなものがあげられます。
-
円滑な話し合いの進行:第三者として関与することで、冷静な協議が可能となります。
-
法的なトラブルを防ぐ:相続人調査や相続財産調査をきちんと行った上で、適正な協議書作成や、必要な手続きをスムーズに進められます。
-
相続人間の不公平感を解消:公平な視点から遺産分割を提案できます。
-
他士業との連携:相続税の申告や登記移転が必要な事案は、税理士や司法書士と連携をとりながら進めていきます。
遺産分割に関するお悩みは当事務所にご相談ください
遺産分割は、円滑に進めることが何よりも重要です。また、その前提としての相続人調査や相続財産調査も非常に手間暇がかかります。
当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、相続人の皆様の立場に立ち、最善の解決策をご提案いたします。事前の調査、話し合いのサポートから、遺産分割協議書の作成、話し合いがうまくいかなかった場合の家庭裁判所での対応まで、一貫したサポートを提供いたします。また、必要に応じて税理士や司法書士とも連携し、相続に関する総合的なサポートを行います。
遺産分割についてのお悩みがございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長