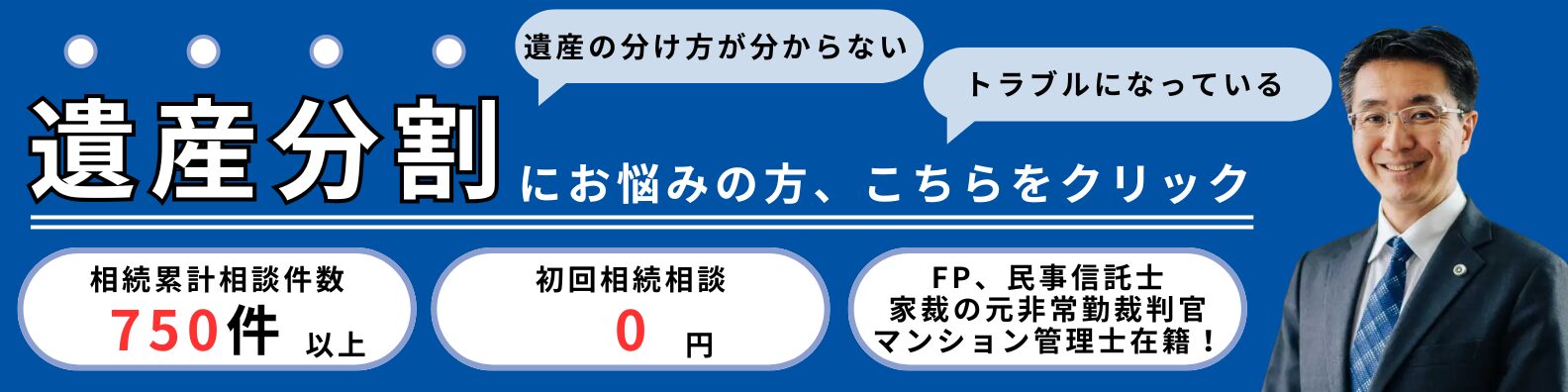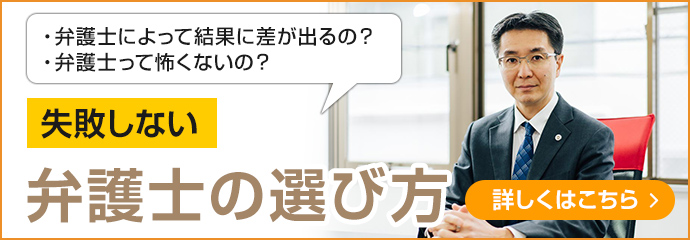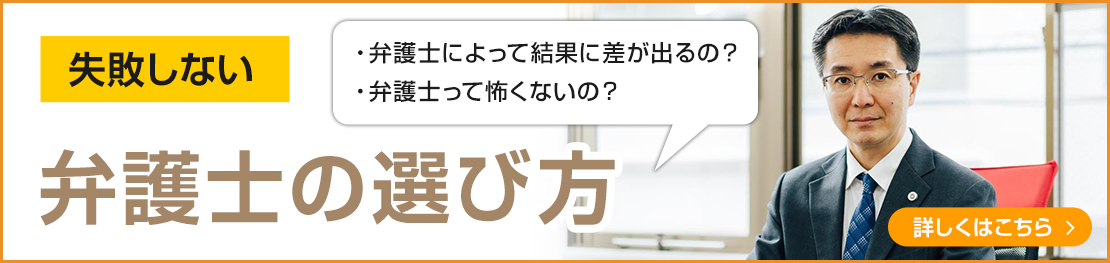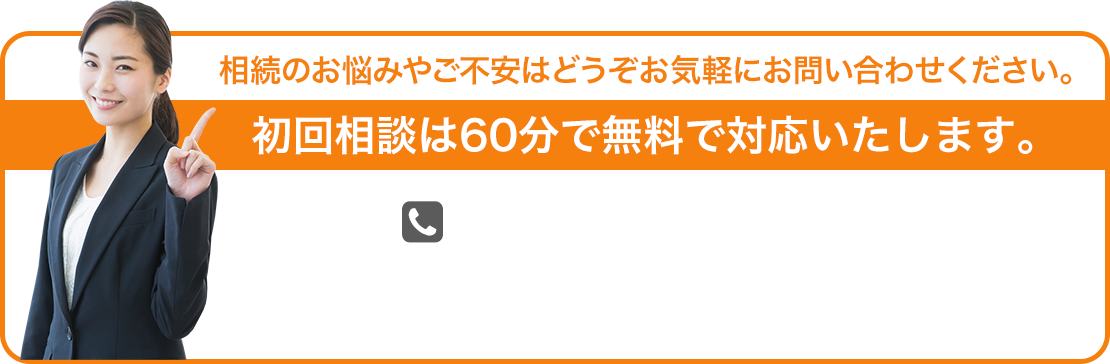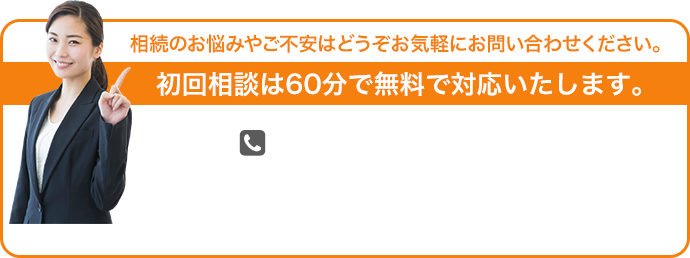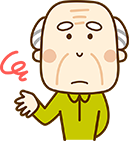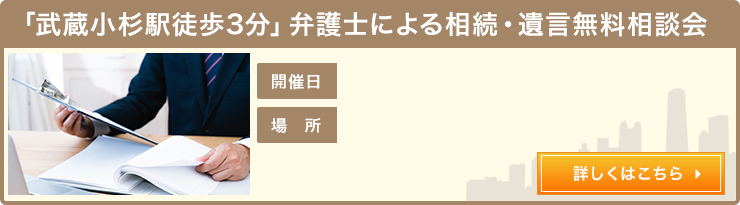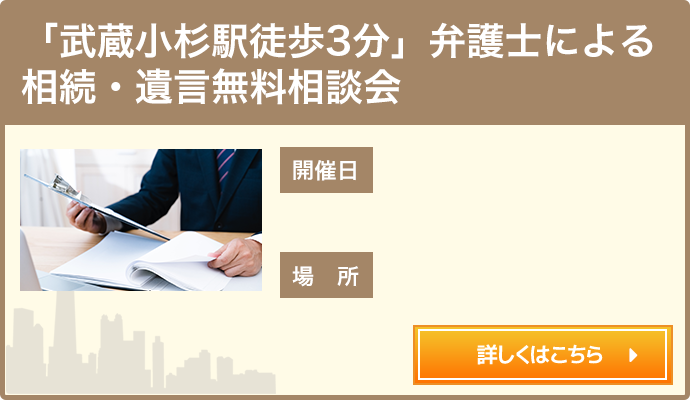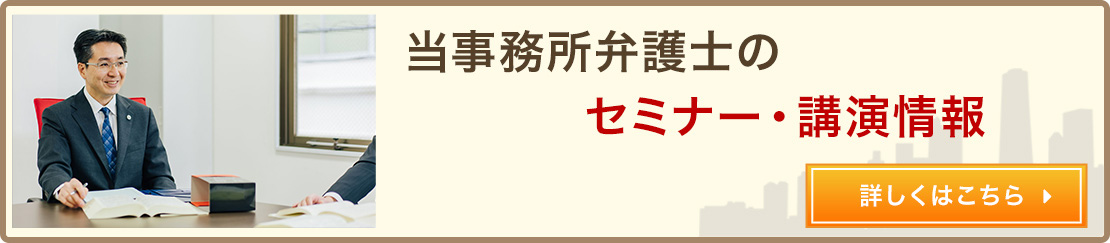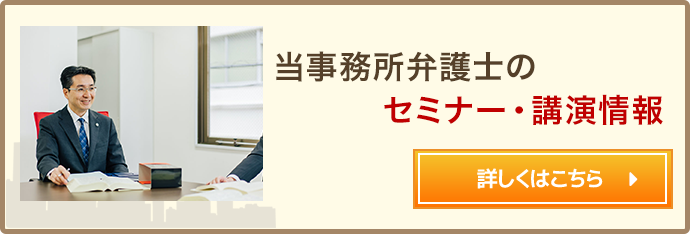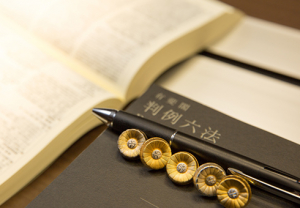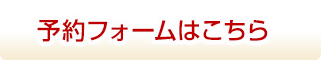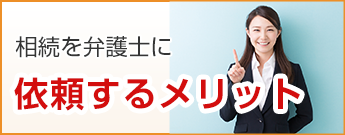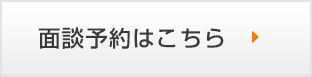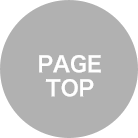遺産分割とは?~手続きの流れや必要書類・注意点を弁護士が解説~
- 2025.12.17
相続が発生したとき、多くの方が最初につまずくのが「遺産分割」の問題です。
何から手をつけていいかわからない
家族で揉めそうで心配
――そんな不安を抱えている方も少なくありません。
このコラムでは、遺産分割の基本的な考え方から、具体的な手続きの流れ、注意点までを、弁護士がわかりやすく解説します。
遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、相続人同士で分け合う手続きのことです。
相続が開始すると、遺産は相続人全員の「共有」となりますが、このままでは相続人各自が自由に財産を使うことはできません。
そのため、誰がどの財産を取得するのかを具体的に決める必要があるのです。
遺産分割の流れ
以下が一般的な遺産分割の進め方です
-
1相続人の確定
被相続人の戸籍を出生から死亡まで取り寄せて、相続人をすべて確定します。
-
2相続財産の調査
預金、不動産、有価証券、借金などを調査し、財産目録を作成します。
-
3遺産分割協議
相続人全員で協議し、財産の分け方を決めます。全員の同意が必要です。
-
4協議書の作成
協議内容を「遺産分割協議書」として文書化し、全員が署名・押印します。
-
5名義変更の手続き
協議書をもとに、不動産登記や預金の解約・名義変更を行います。
遺産分割で用意すべき主な書類
-
・被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
・相続人の戸籍・住民票
・被相続人の住民票除票
・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
・預貯金の残高証明書
・遺産分割協議書(印鑑証明書付き)
遺産分割の4つの方法
遺産分割は状況に応じて、さまざまな分け方が可能です。
これらの方法には優先順位があり、現物分割が原則とされています。当事務所では、「共有」は問題の先送りに過ぎないことが多いため、あまりオススメしておりません。
|
分割方法 |
特徴 |
|
現物分割 |
財産そのものを分ける(例:長男が土地、長女が預金) |
|
換価分割 |
財産を売却して現金化し、その金銭を相続人間で分けあう |
|
代償分割 |
一人が財産を取得し、他の相続人にその価値に見合った金銭(代償金)を支払う |
|
共有分割 |
財産を相続人全員の共有とする(後日分割も可能) |
遺産分割にあたって注意しておきたいポイント
- 相続人全員が揃わないと協議は無効
- 有効な遺言書がある場合は、その内容が原則優先
- 相続税申告は10ヶ月以内、遺産分割の影響あり
- 特別受益・寄与分などの考慮が必要な場合も
揉めやすいポイントを事前に把握し、冷静に進めることが大切です。
弁護士に依頼するメリットとは?
遺産分割は、単なる「話し合い」ではありません。法律、税務、登記、不動産評価、そして何より家族関係という繊細な人間関係が絡む手続きです。こうした複雑な場面で、弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。
-
法律の専門家として正確なアドバイスができる
遺産分割では、遺留分や特別受益、寄与分などの法的概念を理解して進める必要があります。これらは専門知識なしでは判断が難しく、自己流で対応すると法的に無効な協議書を作ってしまうなど、後々トラブルに発展することもあります。
弁護士は法律的なルールをふまえて、客観的かつ適正な分割方法を提示することができます。
-
相続人同士のトラブルを未然に防げる
「兄は親の面倒を見ていなかったのに半分もらうの?」「生前贈与を受けた分は加味すべきだ」
──このように、相続人同士の感情的対立が起きやすいのが遺産分割の現場です。
弁護士が中立的な立場で入り、感情のもつれを整理しながら冷静な話し合いへ導くことで、争いを防ぎ、早期解決につながります。
-
遺産分割協議書の作成を任せられる
協議書の内容に不備があると、不動産登記や預金の名義変更ができなくなります。
また、税務署や金融機関の実務運用も考慮しておく必要があります。
弁護士に依頼すれば、法的に有効かつ実務にも通用する協議書を作成してもらえます。
-
不動産の相続登記や金融機関対応もスムーズに
相続登記は専門的な知識を要する上、自治体や法務局の要件も厳密です。
また、金融機関ごとに求められる書類や手続きが異なるため、時間も労力もかかります。
当事務所弁護士は司法書士などの他士業と連携し、不動産・預金・株式などの名義変更をワンストップで対応できます。
-
話し合いが決裂した場合でも調停・審判に対応可能
協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
その際、弁護士が代理人として関与していれば、スムーズに調停へ移行し、裁判所に対しても適切な主張・立証が可能です。
遺産分割をめぐって調停・審判に発展するケースは年々増加しており、最初から弁護士を関与させておくことがリスク管理の観点からも有効です。
将来的な紛争や相続税トラブルのリスクも軽減
遺産分割が不公平・不透明なまま終わると、「あのときもっともらえていたはず」という不満が残り、親族関係にも禍根を残すことがあります。
また、分割方法によっては相続税の特例が適用されず、余分な税金を支払うことにもなりかねません。
当事務所の弁護士は、懇意にしている税理士などと連携した上で、法務・税務・人間関係を横断的に見据えて対応するため、長期的なトラブルを防止できる安心感があります。
遺産分割のお悩みは当事務所にご相談ください
遺産分割は、法律の知識だけでなく、家族関係への配慮も求められる繊細な手続きです。
「誰に相談してよいかわからない」と悩まれている方は、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、相続手続きを円満かつ確実に進めるためのサポートをいたします。

2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長