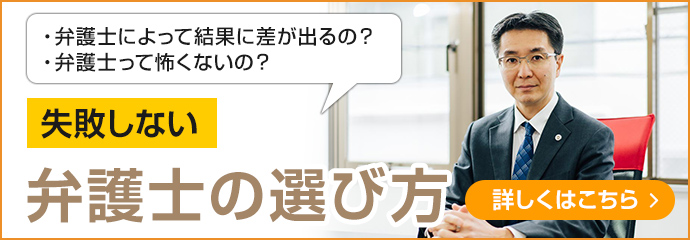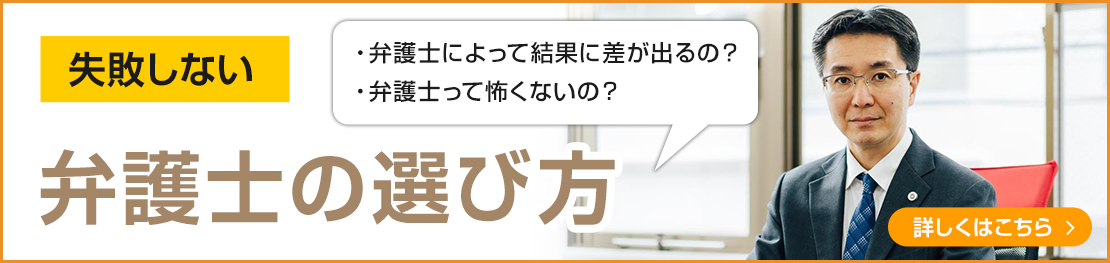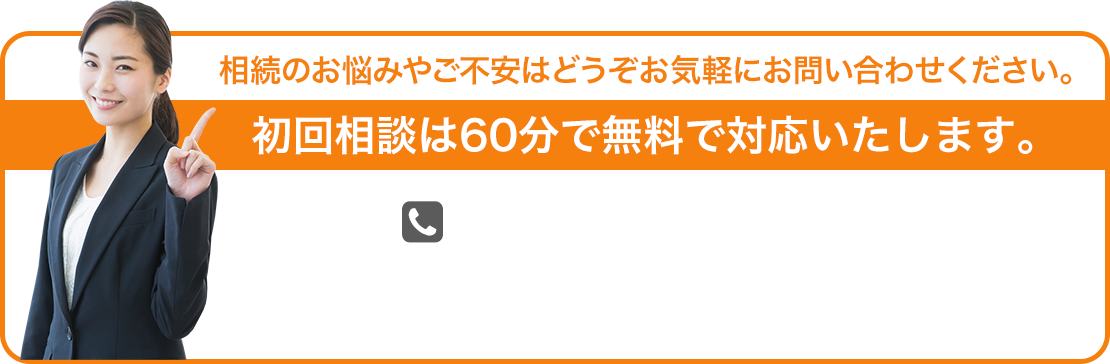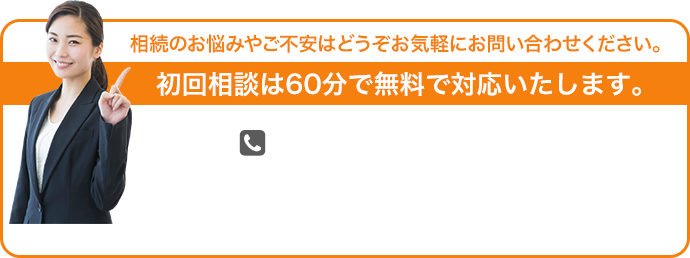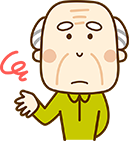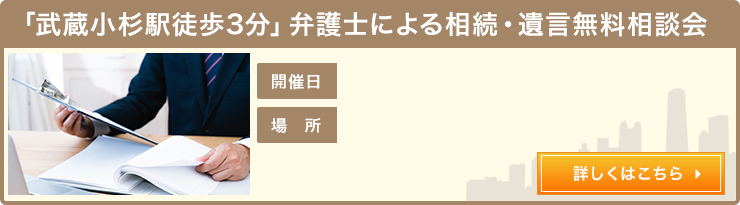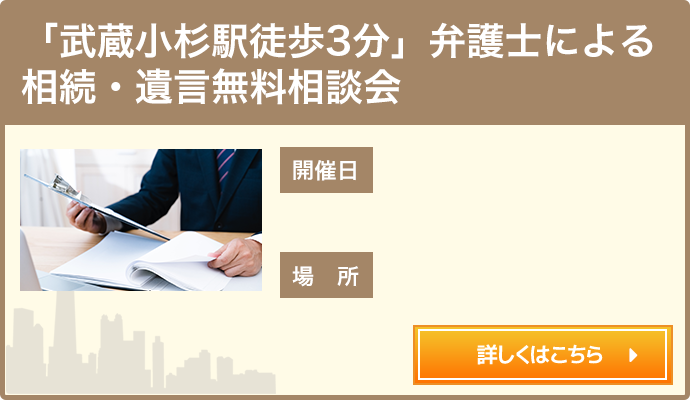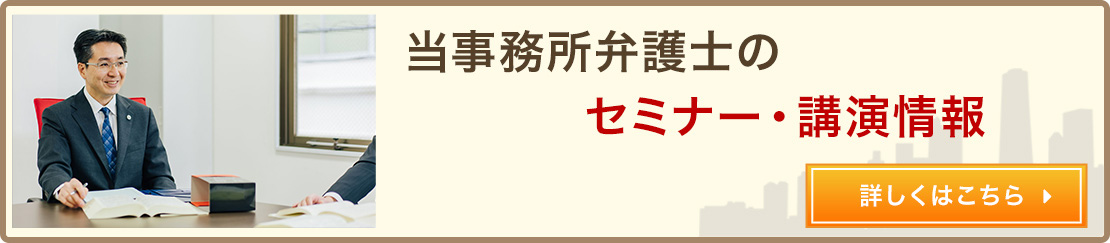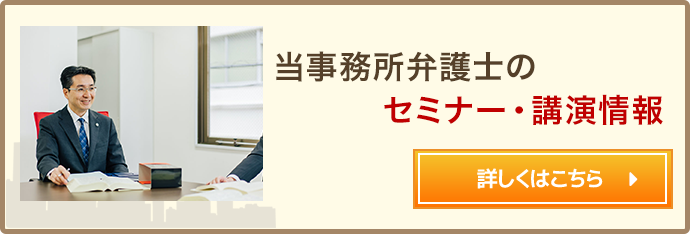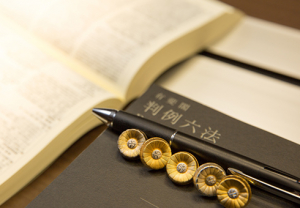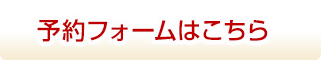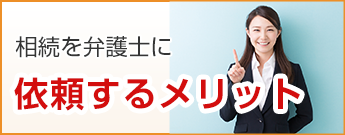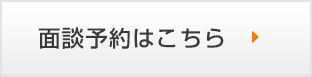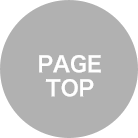遺留分侵害額請求の時効・期限とは?相続に詳しい弁護士が解説
遺留分侵害額請求とは?
相続が始まると、「誰がどのくらい財産を受け取るのか」という問題が必ず出てきます。遺言がある場合、被相続人の意思が尊重されるのは当然ですが、残された家族に一切財産が渡らないような遺言が許されてしまうと、生活に大きな支障が出てしまいます。
そのため法律は、一定の相続人に「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分を保障しています。遺留分は、配偶者や子どもなどの直系卑属、直系尊属に認められており、兄弟姉妹には認められていません。
もし遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」をすることができます。これは遺産をそのまま分け直す手続きではなく、侵害された分を金銭で請求できる権利です。
「遺言などによって取り分がゼロになってしまったけれど、法律で守られている最低限は取り戻せる」――これが遺留分侵害額請求の役割です。
遺留分侵害額請求の時効・期限
遺留分請求には、法律で定められた期限があります。これを過ぎてしまうと、どれだけ正当な主張であっても権利を行使できなくなってしまいます。
消滅時効(1年)
まず重要なのが「消滅時効」です。
相続が始まり、さらに「自分の遺留分が侵害されている」と知ったときから 1年以内 に請求しなければなりません。
ここで大切なのは「知ったとき」というタイミングです。単に相続が始まったと聞いただけではなく、遺言や贈与の内容を把握し、「自分の取り分が足りていない」と認識した時点からカウントされます。
たとえば、相続開始から半年後に遺言書を確認し、そこで初めて侵害に気づいた場合、その時点から1年以内に請求しなければならない、ということです。
除斥期間(10年)
もうひとつ忘れてはいけないのが「除斥期間」です。
相続開始から 10年 が経過すると、遺留分侵害額請求は一切できなくなります。これは「知らなかった」という事情があっても例外はなく、権利そのものが消えてしまう厳しいルールです。
つまり、遺留分侵害額請求には「1年」と「10年」という二重の期限があるという点を、しっかり意識しておく必要があります。
時効を防ぐ方法
「気づいたら期限が過ぎていた」という事態を防ぐには、早めの行動が何より大切です。
内容証明郵便で通知する
相手方に「遺留分を請求します」という意思表示を内容証明郵便で送ることで、時効の進行を止めることができます。口頭で伝えるだけでは法的に弱いため、必ず証拠が残る方法で行うことが重要です。この場合、配達証明付の内容証明郵便で通知すると良いでしょう。
家庭裁判所に調停を申し立てる
相手と直接交渉するのが難しい場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることも有効です。調停や訴訟を利用すれば、手続きの間は時効が完成しません。
こうした方法を知っておくだけでも、大きな安心につながります。
事例紹介
兄弟間での遺留分トラブル
実際に多いのが、兄弟姉妹の間で遺留分をめぐって争いになるケースです。
【事例】
お父様が亡くなり、その遺言には「全財産を長男Aに相続させる」と書かれていました。
この遺言によれば、次男のBさんは何も相続できないこととなりますが、法律上は遺留分が認められています。
Bさんが遺言の存在を知ったのは相続開始から半年後。この時点から1年以内に請求すれば間に合いますが、もし「兄弟だから遠慮して…」と先延ばしにしてしまえば、あっという間に1年は過ぎてしまいます。さらに10年が経てば、たとえ事情を知らなかったとしても権利自体が消えてしまいます。
【ポイント】
遺言を見て「取り分が侵害されている」と気づいた時点がスタート
1年以内に請求する必要がある
期限を過ぎると、正当な権利でも二度と取り戻せない
このように、遺留分請求は「早く気づいて動く」ことが最も重要です。
注意しておきたいこと
遺留分侵害額請求を検討するときには、次の点に注意が必要です。
遺言の無効を主張していても時効は進む
遺言が無効かどうかを争っていても、その間に遺留分の時効はどんどん進んでしまいます。両方の対応を同時に進めておく必要があります。
複数人の請求はそれぞれ別
兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、それぞれが自分の判断で期限を守らなければなりません。誰か一人が請求したからといって、全員の権利が守られるわけではありません。
金銭請求後の時効にも注意
遺留分侵害額を請求したあと、実際に発生する金銭債権にも消滅時効があります。改正民法では原則5年です。請求して安心するのではなく、実際に支払いが完了するまで気を配る必要があります。
弁護士に依頼するメリット
「遺留分を請求できるのは分かったけれど、実際にどう動けばいいのか分からない…」という方は少なくありません。そんなとき、弁護士に依頼するメリットは大きいです。
期限をしっかり管理できる
法的に有効な通知書や書面を作成してもらえる
相手方との交渉や裁判所での手続きを任せられる
精神的な負担を減らせる
遺留分侵害額請求は、専門知識と迅速な判断が必要な手続きです。弁護士に依頼することで、安心して最適な解決に向かうことができます。
遺留分でお悩みの方へ
これまで述べてきたように、遺留分侵害額請求には「1年」と「10年」という厳しい期限があります。権利が侵害されているのでは?と思ったら、できるだけ早く動くことが大切です。
当事務所では、遺留分に関するご相談を数多く解決してきました。初回のご相談で現状を整理し、今後の流れや期限管理について丁寧にご説明いたします。
相続は一生にそう何度も経験するものではありません。だからこそ、安心して任せられる専門家のサポートを受けることをおすすめします。
「この遺言はおかしいのでは?」
「自分の取り分が侵害されているのでは?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの権利を守るために、当事務所は全力でサポートいたします。

2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長