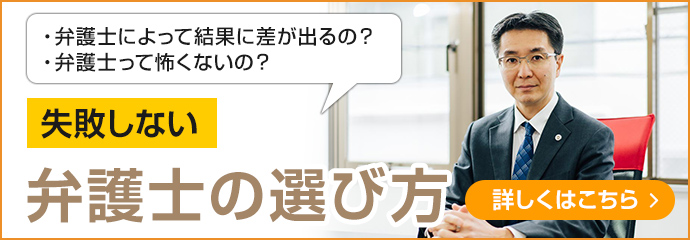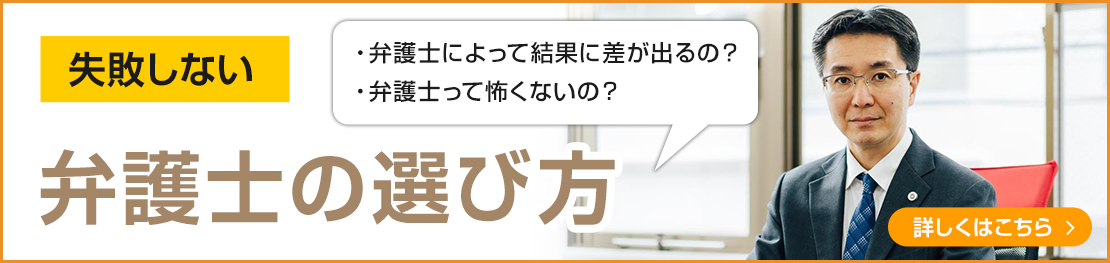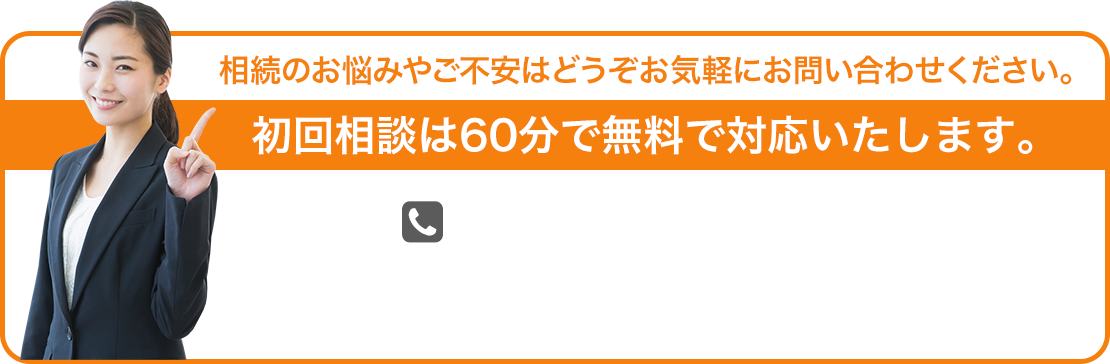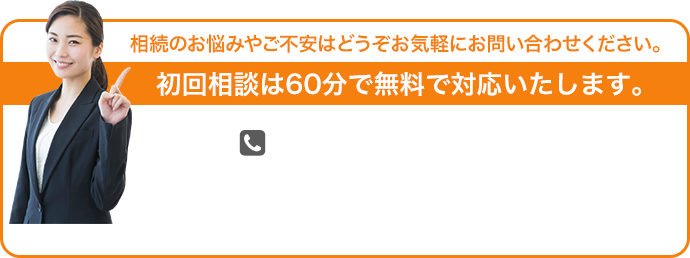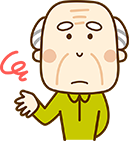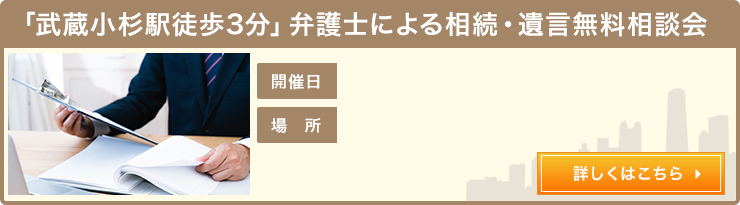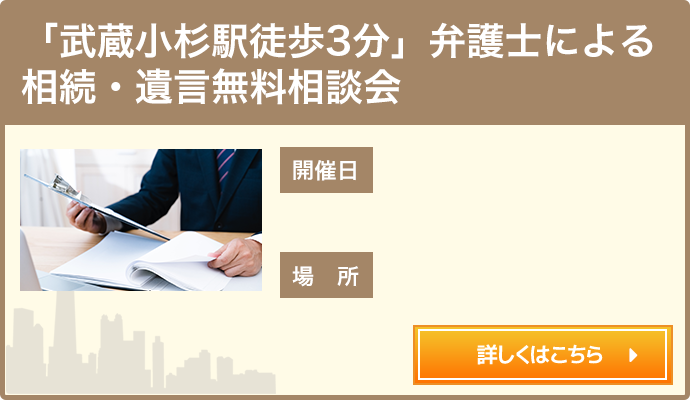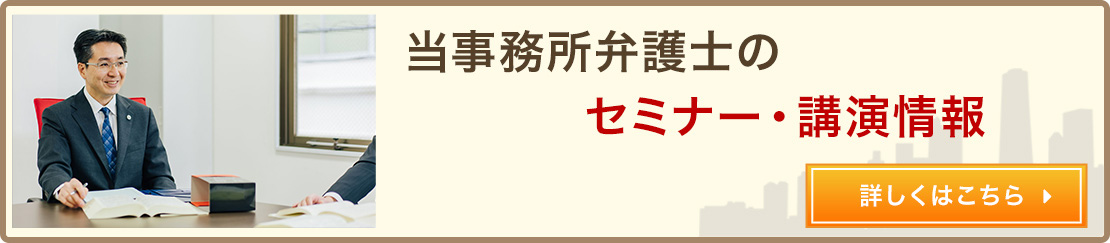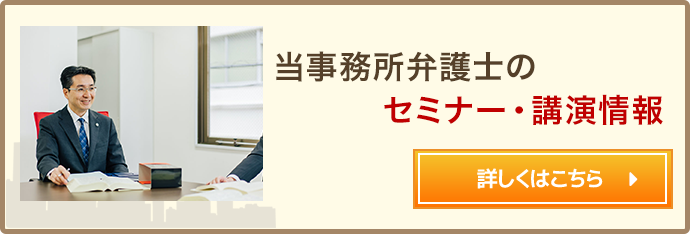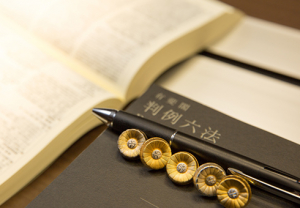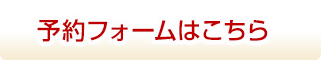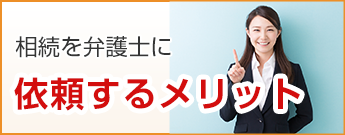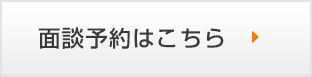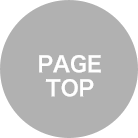遺留分侵害額請求の調停とは?注意点や流れについて弁護士がわかりやすく解説
はじめに
「親が遺言で、兄だけに全財産を残すと書いていた…」
「生前に弟に多額の贈与をしていたと後で知った…」
このようなケースで「自分の取り分(遺留分)が侵害されているのでは?」と思ったことはありませんか?
遺留分は、一定の相続人に保障された“最低限の取り分”です。
もし遺言や生前贈与で不公平が生じた場合、遺留分侵害額請求という法的手段で取り戻すことができます。
しかし、話し合いで解決できない場合は「家庭裁判所での調停」に進むことになります。
今回はこの「遺留分侵害額請求調停」について、流れ・注意点・弁護士に依頼するメリットをわかりやすく解説します。
遺留分侵害額請求調停とは?
そもそも「遺留分」とは?
遺留分とは、法律で保障された最低限の相続分のことです。
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められています。
<遺留分のイメージ>
被相続人の財産:2,000万円の場合
〇配偶者(1/2が法定相続分)
〇子1名(1/2が法定相続分)
→遺留分は法定相続分の1/2
〇配偶者:1/4(500万円)
〇子 :1/4(500万円)
つまり、被相続人が遺言で「全財産を第三者に譲る」と書いても、
配偶者や子は最低でも遺留分(例:500万円)を請求できるということです。
遺留分侵害額請求とは?
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、遺言を一部取り消す方式でしたが、
2019年の民法改正により、金銭請求の形に統一されました。
たとえば次のようなケースです。
父が遺言で「全財産3,000万円を長男に相続させる」とした(相続人は配偶者・長男・次男の3名です)。
この場合、配偶者と次男には遺留分が認められます。
|
項目 |
内容 |
|
総財産 |
3,000万円 |
|
相続人 |
配偶者・長男・次男 |
|
法定相続分 |
配偶者1/2、長男1/4、次男1/4 |
|
遺留分率 |
法定相続分の1/2 |
|
→ 配偶者の遺留分 |
3,000万円 × 1/4 = 750万円 |
|
→ 次男の遺留分 |
3,000万円 × 1/8 = 375万円 |
したがって、長男が全財産3,000万円を取得した場合、
配偶者と次男は合計 1,125万円(750万+375万) の金銭を請求できる、という計算になります。
調停とは何か?
相手と協議しても解決しない場合、家庭裁判所に申立てを行い、
裁判官と調停委員の立ち会いのもとで話し合う手続きが「調停」です。
裁判のように対立する場ではなく、第三者(調停委員)が間に入り、柔らかい雰囲気で話し合いが進められます。
調停で合意すれば、「調停調書」という形の文書となり、法的に強制力を持ちます。
遺留分請求の流れ
調停に至るまでの全体像を整理しておきましょう。
<遺留分請求の流れ>
①内容証明で請求意思表示
↓
②金額を算定して協議
↓
③家庭裁判所に調停申立て
↓
④複数回の調停期日
↓
⑤合意成立 or 不成立
↓
⑥(不成立なら)訴訟提起
内容証明郵便で請求する
まずは、相手(贈与・遺贈を受けた人)に対して、
「あなたに遺留分侵害額請求をします」という意思を明確に伝えます。
この通知をもって時効の進行を止めることができます。
侵害額の算定
被相続人の財産内容(預金・不動産・贈与など)を整理し、
どのくらい遺留分を侵害されたかを計算します。
実務では「遺留分算定基礎財産」の確定が重要です。
家庭裁判所へ調停申立て
協議でまとまらない場合は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てます。
調停委員会が間に入り、話し合いで解決を図ります。
調停成立または不成立
• 双方が合意すれば「調停成立」→調停調書が作成され、法的拘束力が発生します。
• 合意に至らなければ「不成立」→訴訟に移行します。
遺留分請求で注意すべきポイント
時効に注意!
遺留分侵害額請求には2つの時効があります。
①相続開始と侵害を知った時から 1年
②相続開始から 10年
「気づいてから1年」はあっという間に過ぎます。
内容証明郵便の送付で時効を止めておくことが大切です。
資料と根拠をしっかり準備
遺留分侵害額の算定には、
・預金通帳
・不動産登記簿
・贈与契約書
・戸籍関係書類
など多くの資料により、どの財産が遺留分算定基礎に含まれるかを明確にする必要があります。
特に「生前贈与」が絡む場合は、原則として過去10年分まで含まれますので、過去10年分の資産移動も確認します。
調停における交渉の実務
調停では、感情的な主張ではなく、法的根拠に基づいた主張が重視されます。
調停委員に対して、侵害額や算定根拠を明確に示す必要があります。
また、相手が調停に出席しないケースもあります。
その場合、調停は不成立となり、訴訟へ移行する可能性が高まります。
調停成立後の注意点
調停が成立すると、「調停調書」が作成されます。
調停調書は判決と同じ効力を持ち、
相手が支払を怠れば強制執行(差押えなど)も可能です。
弁護士に依頼するメリット
調停は法律知識・交渉力が問われる手続きです。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
正確な算定
財産構成・贈与履歴を精査し、法的に正しい遺留分額を算出
手続き対応
内容証明作成、調停申立、訴訟対応まで一貫して代行
交渉力
法的根拠に基づき、相手や調停委員を説得的に導く
心理的負担軽減
直接交渉や出廷のストレスを軽減
迅速・的確な解決
時効・税務・遺産分割全体を見据えた戦略的対応
<具体例:依頼により早期解決したケース>
事例
父が長男に自宅不動産(評価額2,000万円)を生前贈与。
相続財産3,000万円のうち、配偶者と次男の遺留分が侵害されていたケースで、配偶者と次男から依頼を受けた。
弁護士介入後の流れ
弁護士が財産調査と遺留分算定を実施し内容証明郵便を送付。
任意の交渉で解決できなかったため、調停で「配偶者750万円、次男375万円」の請求を法的根拠に基づき主張。
3回の調停期日で合意成立し、合計1,125万円の支払いで早期解決。
「感情的な対立」ではなく、「法的な説明」を徹底することでスムーズに解決できた好例です。
遺留分に関するお悩みは当事務所にご相談ください
遺留分侵害の問題は、時間との勝負です。
時効の進行、証拠資料の確保、感情的な対立など、放置すればするほど難航します。
当事務所では、
• 遺留分侵害額請求の可否判断
• 内容証明の作成
• 調停・訴訟の代理
• 円満解決に向けた交渉戦略
まで一貫してサポートいたします。
相続・遺留分に詳しい弁護士が、法的にも感情面でも寄り添いあなたの立場を守りながら、最適な解決を目指します。
遺留分に関するご相談は「武蔵小杉あおば法律事務所」へご相談ください。
当事務所では遺留分に関する紛争を数多く扱った経験があります。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長