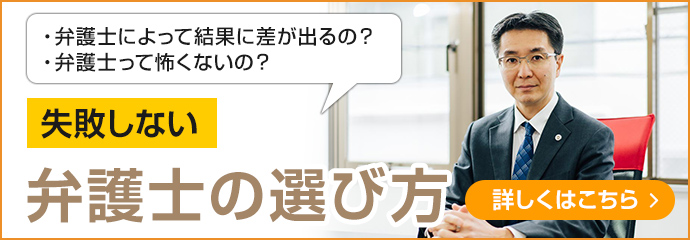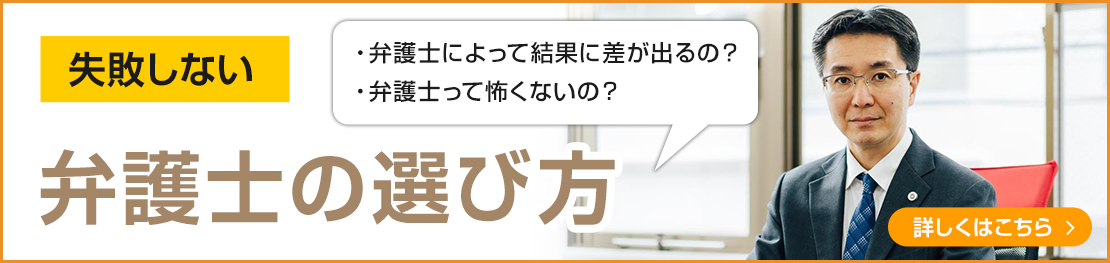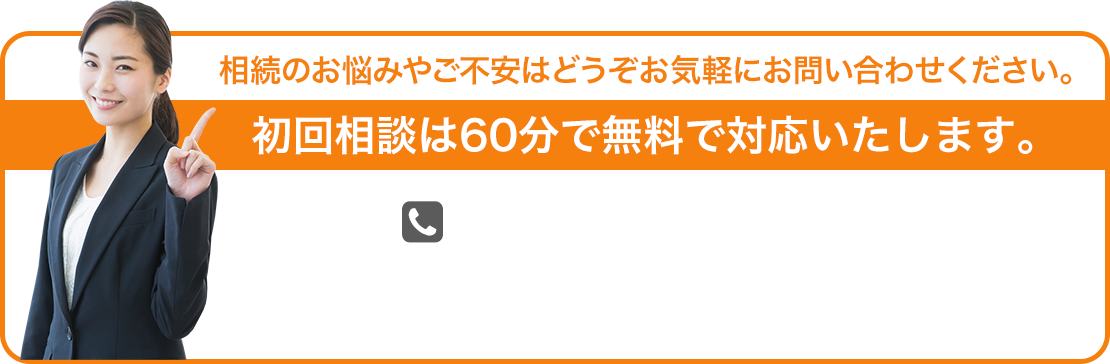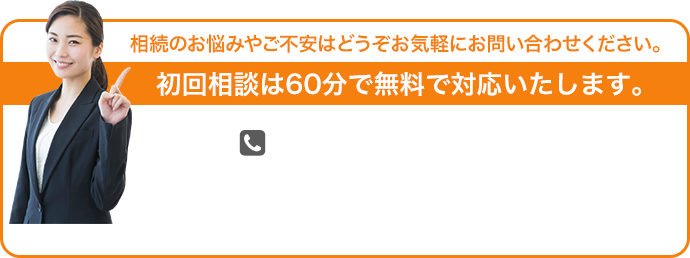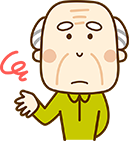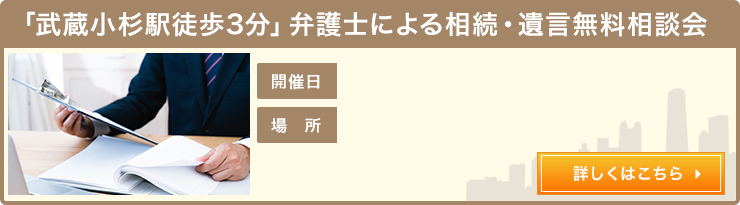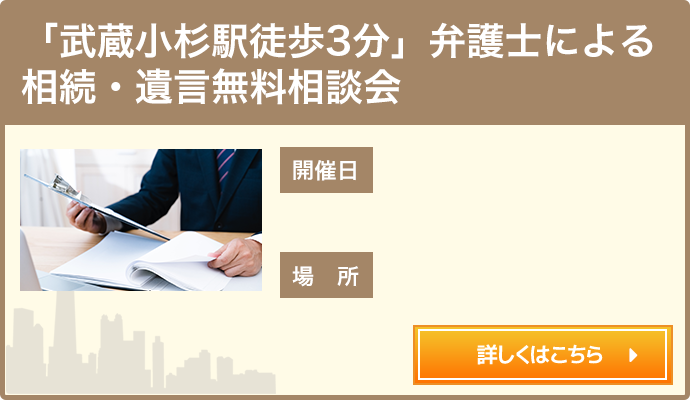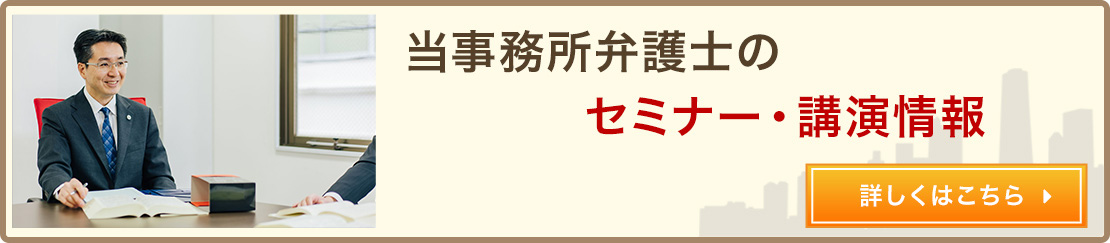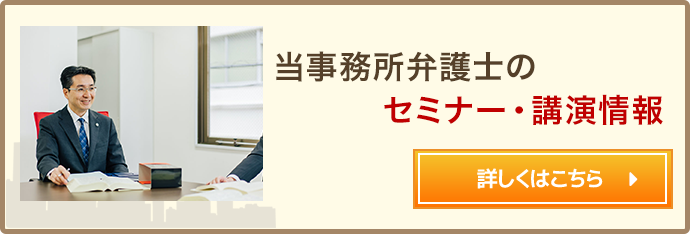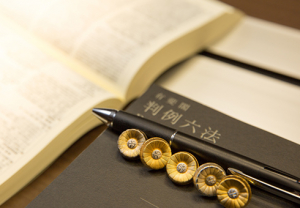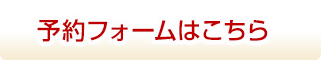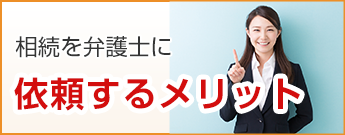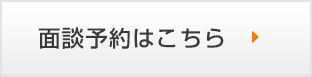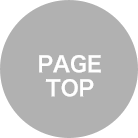相続人である弟に連絡を無視され、実家の処分に困っていた事例
- 2025.10.09

【相談者の属性】
年代
50代
性別
男性
【相談内容】
相談者のお母様は2年前に亡くなりました。相続人は相談者ご本人と弟2名の合計3名でしたが、うち一人の弟とは、折り合いが悪く、相談者が手紙や電話で連絡を取ろうとしても、何の反応もありませんでした。業を煮やした相談者が弟の自宅を訪問し、インターホンを鳴らすも反応がなく、置手紙を残したものの、やはり連絡はありませんでした。
お母様が生前住んでいた住宅があり、空き家になっていましたが、このままでは固定資産税がかかるばかりであり、また相談者のご自宅からは距離があるため、維持管理の手間もかかります。なんとか処分したいということで、ご兄弟2名で弁護士にご相談されました。
【弁護士の対応】
まずは弁護士名で受任通知を送付し、通知が到達したことで、住所に現住していることを確認しました。受任通知にも対応がなかったことから、今後も任意の交渉ではおそらく手続に関わってこないだろうとの予想を立て、裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。従前の経緯や審判の必要性に関する資料を弁護士が作成して裁判所に提出し、迅速な進行を求めました。
【結果】
裁判所で相手方が欠席する期日が複数回続いたところで、相談者は空き家の代償金の支払義務を負う一方で、実家を取得する内容で調停に代わる審判がなされ、確定しました。この調停に代わる審判というのは、当事者が何らかの理由で裁判所に出廷できない場合に用いられる手続であり、実務上よくあるケースでは、それまで調停の内外で話し合いができており、合意に至っていることを前提として、当事者が健康上の理由や、裁判所から遠方に居住していることを理由に、出廷の手間を省くために利用するものです。もっとも、今回のように、相手方と全く連絡がとれない場合でも、公平性が確保されると裁判所が判断した場合に適用されることもあります。
審判の確定後、相談者は速やかに不動産業者に売却を行い、ご実家の維持管理の負担から解放されることができました。
【弁護士所感】
相続に関するご相談で、相続人に関して問題になる典型的なケースは、相続人同士が疎遠であるなどして、その所在が分からないというケースや、相続人の関係が悪化しており、連絡が取れない、話し合いが進まないといったケースです。多くの場合、弁護士名義の通知を送付したり、裁判所で遺産分割に関する手続を申立てたりすれば、何らかの反応があるものですが、今回のケースは、全く連絡がつかないという少し変わったケースでした。
このような場合でも、適切な手続を選択すれば、事案に応じた適切な解決に至ることを期待できます。
当事務所では同様の案件について豊富な実績がございます。
同じようにお悩みの事案がありましたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長